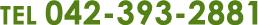ストレス時代をたくましく生き抜く ①ストレスってな~に
2025.11.19
現代人は、変化の速い社会の中で時間に追われ、複雑な人間関係に悩まされ、多くのストレスを抱えていると言われていて、 日常生活の中でも、“ストレス”という言葉はとても気軽にいろいろな場面で使われています。例えば、「最近ストレスがたまっている」とか「運動でストレス発散しよう」などのように。でも、あまりに幅が広すぎて、ストレスっていったいなんなの?と思ったのでちょっと調べてみました。もともとこの言葉は物理学で使われていて、「外からかかる力による物質の歪み」を意味していたのですね。この言葉を医学領域に取り入れてストレス学説を提唱したのがカナダの生理学者であるハンス・セリエ博士(1907-1982)です。博士は生体に作用する外からの刺激に対して、体に生じたひずみ(生体の非特異的な反応)の総称をストレス状態と定義しました。そして、外からの刺激に対するからだやこころの反応のことを“ストレス反応”と呼び、その反応を生じさせる刺激(ストレスの原因)のことを“ストレッサー”と呼びました。
現在一般的に用いられているストレスはこの両方の意味を含んでいるようです。つまり、ストレスとは外部環境の種々の要因が変化したとき、それが刺激となって生体に様々な機能変化が起こった状態ということになります。ストレスの原因としては、物理化学的(熱、音、放射線、化学物質、酸化還元状態の変化など)、生物学的(感染、寄生虫など)、精神的(緊張、不安、恐怖など)なものなどが挙げられています。多種多様です。また、これらの刺激を受けて変化する生体機能も様々です。きわめて日常的に共通に体験される精神現象であると同時に、筋肉の緊張や不眠などのさまざまな生理的変化をともなった身体的現象でもあります。重要な特徴として主観的・相対的であることが挙げられます。
看護部顧問 坂田 三允